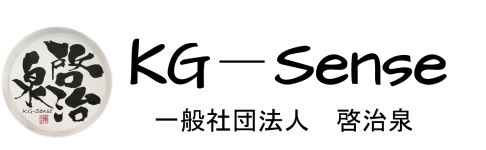理念
「いくつになっても、どんなカラダになっても、昨日と同じ生活を、不自由なく送り続けたい」
「もし、この瞬間に大けがや病気に見舞われて、障害が残っても、これまでと変わらない生活を送り続けたい」
「普通のバスケは苦手だけど、車いすバスケなら活躍できる気がする」
--誰もが願う理想的な生活や、新たな目標となり得る選択肢の増加ですが、果たして様々な商品やサービスの作り手が「自分事」として、つまり「当事者意識」を持って、日々取り組んでいるのでしょうか--

一方、人間は『言語』で自己表現し、『言語』で他者を理解しようとします。
しかし、『言語』だけでは伝えきれない思いや感情があり、代わりに『音楽』で表現することがあります。

それとは別に、物理的身体的理由で、音楽を奏でること、音楽を聴くことをあきらめている人々も多くいます。
--『音楽』には、心を安らげる作用があることは、言うまでもありません--
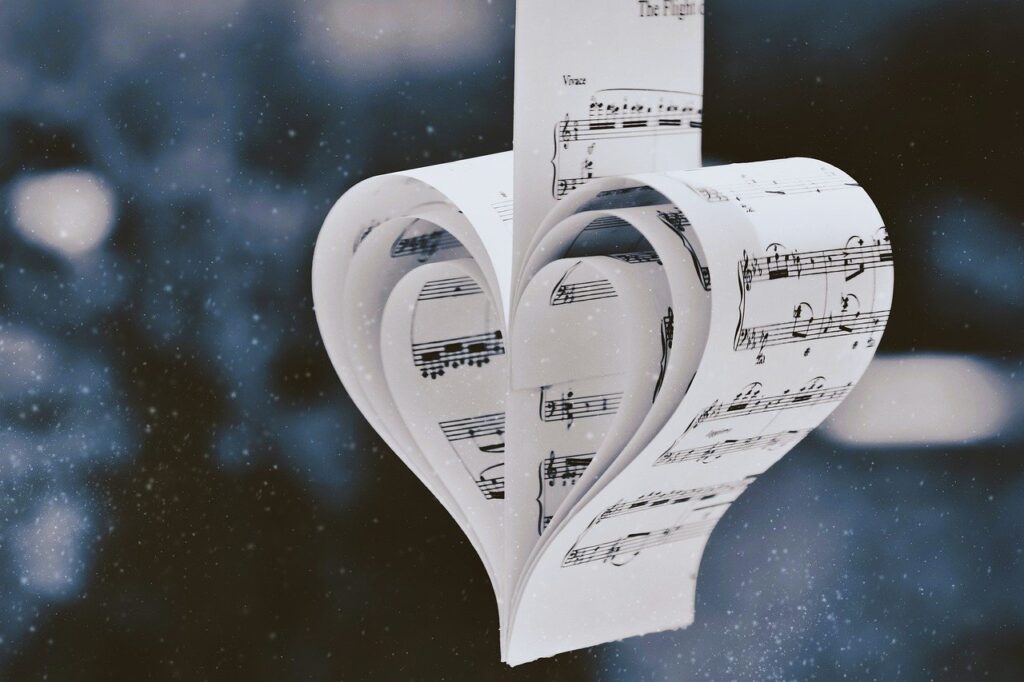
けして「福祉」の枠に留まることなく、
既存の商品やサービスに少しの工夫を加えるだけで、
「明日の自分」が今まで通りに生活できるように。
さらに、今まで視界に入っていなかった潜在顧客やパートナーとの「出会い」を。
一方、現在「福祉」の枠で生活されている方々にも、
多くの人々と同じ商品やサービスを使うことで
「枠に囚われない他者との繋がり」「便利な生活」「日常生活を彩る楽しさ」を。
啓治泉では、これらの「理念」に基づいて、ご提案や実現を推進いたします。
ユニバーサルデザインとは?
-バリアフリーとの違い-
「ユニバーサルデザイン/バリアフリー ぷらざ」さんによる大変わかりやすい説明を引用します。(註:太字は弊法人による加工)
ユニバーサルデザイン・バリアフリーぷらざ〈ゆびぷら〉※外部サイト「ユニバーサルデザインは、障害者だったロナルド・メイス氏が、バリアフリー対応設備の「障害者だけの特別扱い」に嫌気がさして、最初から多くの方に使いやすいものを作る設計手法(註:太字は弊法人による加工)として発明されました。
一方、バリアフリーは障害者・高齢者などの生活弱者のために、生活に障害となる物理的な障壁の削除を行うという、過去の反省に立った考え方で進化してきました。
バリアフリーは、障害者・高齢者などに配慮されて策定していますが、ユニバーサルデザインは、個人差や国籍の違いなどに配慮しており、全ての人が対象とされています。
また、普及の方法も大きく違い、バリアフリーは法律等で規制する事で普及させる「行政指導型」ですが、ユニバーサルデザインは、良いものを褒めたたえ推奨する「民間主導型」と大きく異なっております。
「多くの方に使いやすいものを作ってあげよう」というユニバーサルデザインの思想には『心のやさしさや思いやり』があります。また、「障害者、高齢者等が安全に円滑に利用できるだれもが住みよい福祉のまちづくり」を行うバリアフリーにも『心のやさしさや思いやり』があります。
この共通する『心のやさしさや思いやり』の精神は、「すべての人を個人として尊重し、思いやりの心を持って助け合う態度を育て、共に生きる人間の心の育成を目指す」福祉のこころの育成に通じているのです。」とあります。
ユニバーサルデザインの可能性
-「福祉」ではなく-
弊法人では「ユニバーサルデザイン」を「福祉」とは考えていません。なぜなら、「誰にとっても便利」であることは、「あらゆる人に当てはまる」ことを意味するためです。つまり「今日の自分」が、突如事故や疾病によりカラダの機能に支障が生じても、「明日の自分」が何ら問題なく「今日の自分」と同じ生活を送るために、「今日の自分」でも「明日の自分」でも同じように利用できる商品やサービスの普及を目指しているためです。
また、高齢者になると、手足が思うように動かなくなったり、見えにくさや聞こえにくさが進んだり、いわば誰でも「障害者」になります。このように「自分にも起こりうること」という「当事者意識」こそが、「ユニバーサルデザイン」推進の重要なカギになる、と弊法人は考えています。「福祉」という枠、つまり、自分との間に「壁」を作ることによって「自分とは無関係な他人事」のように錯覚し、「当事者意識」が生まれにくいことが、現状大きな壁や隔たりを生んでいる、と考えます。
一方、ビジネスの観点から言うと、既存の商品やサービスに「ユニバーサルデザイン」の要素を加えると、マーケットが飛躍的に拡大します。実際、「福祉機器」と呼ばれるモノが家電量販店に並んでいてもおかしくはなく、当然その逆のパターンも見受けられます。しかしながら、これに関しては、日本の福祉に関する法制度も関連するため、枠や壁を軽やかに超えるまでには時間がかかることでしょう。もちろん、程度によっては、専用の「福祉器具」「福祉サービス」が必要です。だとしても、「今日の自分と地続きにある」という「当事者意識」が、より専用の器具やサービスの進化につながるのではないでしょうか。
アマチュア音楽家支援
-ユニバーサルデザインの観点から-
太古の昔、人類が言語を発明する前から、「音」による自己表現やコミュニケーションは存在していました。やがて、「文化」として「音楽」という分野が確立します。これは、「音」が単なる合図や伝達の手段ではなく、人間には言語化できない感情や考えを持っていること、ひいては言語より雄弁に自己表現できること、言語による自己表現では味わえない「何か」を得られることの証とも言えます。
同様に「音楽」を受け取ることは、言語による表現や理解とはまったく異なった脳への影響があり、人間性を多面的に豊かにする役割、いわば「人間を人間足らしめる」一助となりえます。
しかしながら、身体的な理由などによって「音楽」に触れることが困難な方々がいらっしゃるのは残念な事実です。すでに「音楽に国境はない」と認知されているのですから、どのような環境に置かれている方でも「音楽」に触れられるチャンスを増やすことで、たくさんの人々の生活に彩りを加えていきたい--これも「ユニバーサルデザイン」につながる弊法人の活動と位置付けています。